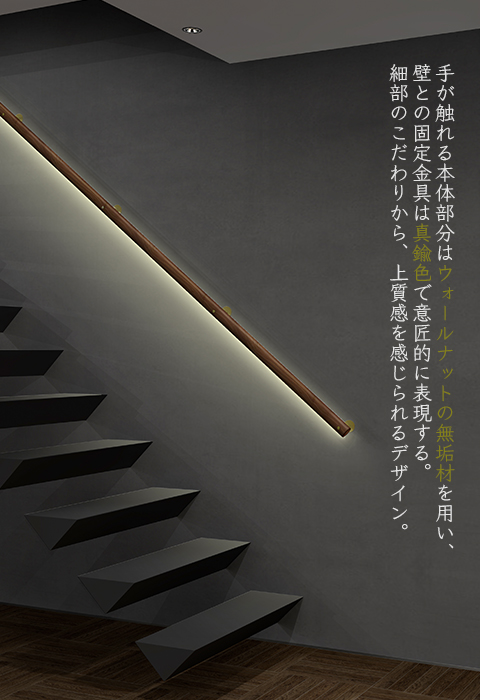プロの住宅レシピ 景色と時間をデザインする──窓と光が導く健やかな暮らし

北海道札幌市。お施主さんご夫婦と3人のお子さんのために計画された平屋の住宅。 お施主さんの希望は、住戸棟と車庫棟を2つ並べた配置計画、風水に配慮した四角い間取り、そして南側に広がる公園の景色を取り込むことでした。
直線的でシンプルな構成を望まれたことから矩形を基調に整え、公園に隣接する立地を最大限に活かして公園側に庭を計画し、各室からの庭や公園との繋がりを軸に進められました。
この住宅の最大の特徴は窓。公園側に設けられた南洋材のニヤトーの木製サッシは、室の用途に応じて3種類設計。
LDKに面する窓は、間口7.2mのヘーベシーべ窓で、両端をFIX、中央を開閉式とすることで操作性と景色の連続性を両立。
客間に面する窓は、腰掛け高さの出窓空間をヌックとしており、子どもたちの遊び場や庭を眺められる読書スペースとして機能しています。横桟を特徴としたルーバー網戸もニヤトーで造り、日射の遮蔽と通風の役割をもちます。
寝室に面する窓は、庭を眺めるためのFIX窓と通風のために板戸を引き上げて確保する仕掛けを設計しています。
窓の位置とサイズは外装材の道南杉の板幅と割付で細かく決めています。桟の細さや横桟のラインは一つひとつ図面を描き込んで調整され、大工さんの高い精度が空間全体の美しさを支えています。
もう一つの軸は照明。サーカディアンリズムに基づく自動調光調色機能を備えた照明を全室に導入し、お施主さんの希望であるスマートな暮らしを実現しています。
食卓の料理を美しく見せるなど暮らしのシーンに呼応して音声操作やスマートフォン制御まで細やかにカスタマイズ。光のグラデーションが家全体の表情が豊かに広げます。
完成後の暮らしは、キッチンに立てば広い庭とリビングやダイニング、客間で過ごす子どもたちの遊びや勉強の様子が一望でき、間口を敢えて広めに計画した中廊下のピアノスペースにも気配が届きます。
夏はエアコン一台で全体が涼しく、冬は床暖房だけで心地よい断熱性能が家族の時間を支えています。
窓が景色を導き、光が時間を整える──そんな快適な日々の暮らしそのものがデザインされた、日常を包み込む住まいです。